
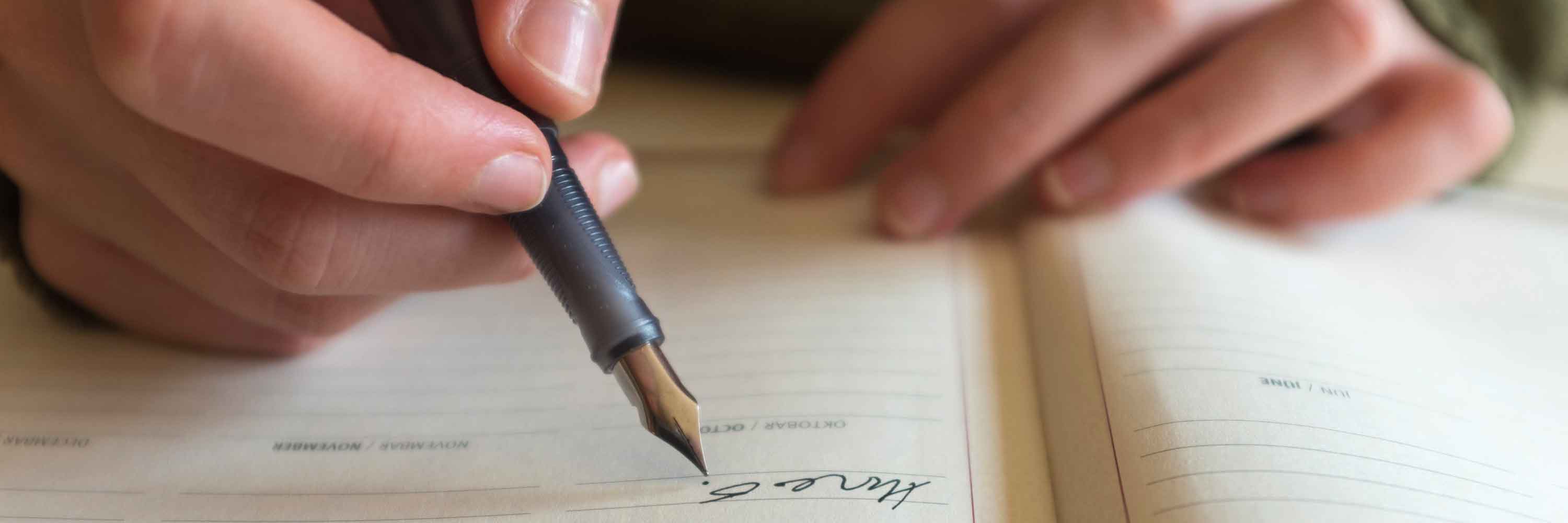

日本拳法は昭和七年に宗家である澤山宗海により、設立された。澤山宗家はもともとは柔道家であったのだが、講道館は危険とされる当て身・関節技を排斥していた。しかし、澤山宗家は「投げる前に殴るだろう」という発想を長年にわたって抱いており、空手(当時は唐手)の糸東流開祖の摩文仁賢和に教えを受けていたことがあった。しかし、当時の空手は自由組手のない型稽古だけであった。澤山宗家の実戦性への追求、そして研究は並々ならぬものがあったのであろう。当時としては斬新な防具(鉄面、グローブ、胴衣、股当て)を作り、乱稽古ができるようにしたのである。その組織は大まかには、宗家がつくった元祖の日本拳法会と日本拳法連盟が主流であり、その流れから移った流派もある。以前は関西は伏拳(ふせけん)、関東は縦拳(たてけん)と言われていたが現在は選手それぞれの好みで使われているそうだ。ルールは剣道と同じ三本勝負。打撃による気合・撃力の伴ったと判定されたものが一本、もしくは投げてから抑え込んだり、体の自由を奪ってからの打撃が判定のポイントになる。さらに、腕肘逆十字などの関節技も認められるほか、肩固め(相手の脇に攻撃者の腕を入れて攻撃)という極め技もある。また、これも日本拳法独特のルールだが、股蹴りもあるそうだ。相手の蹴り足をキャッチして、相手の金的を蹴るのも一本。さらに、投げ飛ばした相手の面から胴をその場で踏みつけるという踏み蹴りもある。ただし、思いっきり蹴るのではなく、軽く蹴るだけでの一本という判定になっている。寝技もあり、決まり手は膝一本が多い。四点ポジションでの頭部への膝蹴りは殆どの武道で禁止となっているが、日本拳法では抑え面膝、迎え面膝で一本になっている。反則は防具装着箇所、面・胴以外への打撃。近代武術ではないので、ローキックのような蹴り技はないそうだ。もともと、母体が講道館柔道なので足払いが巧みな選手が多く、開始即タックルも認められている。試合時間は一般戦がだいたい三分、トーナメント制だと二分、マスターズだと同じく二分。ちなみに鉄面の厚さは8ミリで重さが2,7kg。タオルを面内に二枚着衣するので約3kgという結構な重さになる。そのあたりはかなり、フィジカルの強さが求められるそうだ。ちなみに胴衣は剣道の胴とも違い、下胴といって、木綿の厚めの緩衝材が入った胴になっている。グローブは8オンスだが、組み技があるので親指が開けられるようになっている。簡単ではあるが、以上が日本拳法の説明になる。

ここからは今回、紹介する新田龍一の紹介文になる。武術との出会いは八歳の頃から少林寺拳法をやったていたそうだ。通っていた小学校で夜、稽古が行われていたので入門したのである。中学入学後は部活で三年間、柔道部に在籍していた。高校に進学した以降は一年から三年まで某フルコンタクト空手を学んでいた。その後、九州で初めて設立されたキックボクシングジムに入会し、一時的に通っていたそうだ。また、個人的に知り合った海外で指導員補佐をしていた空手家に個人指導を受けていた時期もあったそうだ。
「その後、武道からは七年ほど離れていたのですが、当時、地下格闘技が始まり出していたのです。自分の実力を試したくて出場したのですが、二ラウンド目にキックボクサーにTKO負けをしてしまいました。その時、セコンドに就いてくれていた昔の空手仲間が子どもに空手を習わせていたのです。その横のレーンで日本拳法をやっており、『それが本当に凄い!』という話を聞いて、見学に行ってその場で入門しました。その時点で34歳だったのですが、始めのうちはパンチが当たらなくて、相手から殴られ放題でした。フルコンタクト空手をやっていた時の癖で間合いが近かったのです。その癖を修正するのに何年もかかりました」
ちなみにその道場(体育館)は自衛隊駐屯地の近くにあり、自衛隊の選手が大会前になると部隊で練習に来ていた。モンスター級の選手が何人もいたので、彼らとの練習が新田にとって貴重な体験になったのである。
「乱稽古では剣道の踏み込み(体当たり)に拳が乗ってくるような重量級のパンチが飛んできます。だから、足さばきと踏み込みを日本拳法では何年も指導されます。蹴りの間合いからパンチが飛んでくるので、他の格闘技・武道をやってきた人にとってはやりにくいようですね。日本拳法のいいところは殴り合いの頻度が高いので、面があるとはいえ、パンチに対する恐怖心を克服できることです。また、徒手の武術として非常に即用性と実用性が高いと思われることと、柔道・剣道のように比較的、安全に実際の乱稽古ができることも魅力と言えるかもしれません」
自分の少ない知識から書くと、自衛隊では徒手格闘術と呼ばれている。それを新田に訪ねると、日本拳法全国連盟の傘下に全自衛隊拳法があるらしい。自衛隊に所属する彼の知人の話によると、「自衛隊拳法」という名称になっているそうだ。大会には自衛隊からの出場が数多い(大学の部活も多い)らしいが、とにかく強いと言う。いずれも、人並外れた強豪揃いらしいが、その一人が現在、MMAで活躍する木村柊也である。明治大学在校中は全日本学生拳法選手権を3連覇、プロデビューしてからも4戦全勝、全て初回KOを誇っている。その他、プロボクシングで世界チャンピオンになったり、K1で活躍する選手もいる。そのような背景を見て、新田に「プロを目指したいとは思わなかったか?」と質問をなげかけると、「さすがに年齢的にプロは考えませんでした」という回答が返ってきた。謙遜しながらの答えだが、試合中の動画を何回も送ってもらい、実際の彼の戦いぶりを見ている自分から言えば、十分に強いと思えるのだ。

新田との会話の中で特に気持ちを惹かれたのが波動拳という日本拳法独自の打ち方である。その打撃の体得に磨きをかけている彼にその説明をしてもらった。「構えの手を開いて、できるだけ手首を反らし、脱力して構えます。突きを放つ際は足から足首、腰、肩と波がうねるように開手のまま目標に打ち出します。当たる直前に拳を握り、手首のスナップを活かして、全身で打ち抜く打撃法です。それが自然とできるようになると、体の動きが理にかなったものになるんです」
柔らかい構えから一気に強力な突きを放つ打ち方は蹴り技にも応用されているらしい。練習内容は基本の突き・蹴りをやって、乱稽古に入る。乱稽古にも実乱(スパー)と空乱(マススパー)があるらしい。
最後に新田がこれからどのような目標を持って、日本拳法に取り組んでいくかを聞いてみた。
「武術は辞めずに歩みを続けて行けば、必ずどこかのゴールにたどり着くことができます。自分は今、カウンター狙いに磨きをかけていますが、無駄のない動きで勝利を治められるような戦いを体得したいと思っています。話は変わりますが、武術とか格闘技で多少、殴り合いが強くなったところで、世の中も周りも変わらないんですよね。それでも強さ=気持ちの余裕になるので、弱い人を助けることができます。それが武術の一つだというのが自分の考え。それから、日本拳法は続けていきますが、新たな武術も学んでいきたいと思っています。それらを探求することで、理にかなった体の動きを身につけたいと思っています。今まで何度となく試合には出てきましたが、改めて思うのが興行や試合が全てではないということ。人と比べても仕方ないんです。武術とは自分と向き合うもの。江戸時代の剣豪で天然理心流の近藤周助邦武が『剣術なんてえものは試合で勝とうが、負けようがどうでもよろしい。不断にやっておりさえすれば、いざというとき役立つもんさ。役立てねえのは心がいけねえ』という名言を残しています。フィジカルな強さも磨いていきますが、そのような心の強さをも自分のものとなれるよう、武術の道を目指していきたいと思っています」